高校生物の問題演習
五界説とドメイン
※広島大学の入試問題を参考に作られています。
生命の進化に関する次の文章を読み、問1~問4に答えよ。
約40億年前に単元的に誕生した原核生物は、その進化の過程において、どのようなルートを歩んで、現在の約1500万種を越えるとされる多様な生物を生みだしたのか。米国のカール・ウーズは、核酸の配列からこの疑問に答えようとした最初の一人である。
従来、生物を系統的に分類する方法としては、1960年にコーネル大学のR.H.ホイッタカーによって提唱された「五界説」が主流であった。彼によれば、生物は五界(グループ)にまとめられるという。すなわち、細菌類を一群にまとめた「 ア 界」,ゾウリムシやアメーバなどの単細胞生物をまとめた「 イ 界」, イ から摂取によって栄養を獲得するという方向に進化した「 ウ 界」,吸収によって栄養をとる方法を発達させた「 エ 界」,そして光合成により栄養をとる方法を発達させた「 オ 界」である。こうした従来の説に新しい息吹を吹き込んだのが、タンパク質やDNA,RNAに残されている分子進化の痕跡を調べる分子系統学である。分子系統学では、はじめはタンパク質であるチトクロームcのアミノ酸配列を比較して、生物間の分岐年代を推定していた。それがやがて、16SリボソームRNAや5SリボソームRNAの遺伝子など、核酸の塩基配列を比較するようになった。
こうした分子系統学の最大の成果といわれるのが、1970年の中頃、前述のような、ウーズが提唱した、生物界を三つの領域(ドメイン)に分類する三ドメイン説である。本書も基本的にはこの分類法に従っている。ウーズは、原核生物や真核生物がどのように多様化したかについて、リボソームの小サブユニットを形成するrRNAの遺伝子、すなわち原核生物では16Sリボソーム遺伝子注1)、真核生物では18Sリボソーム遺伝子注2)の塩基のカタログ(塩基配列)を比較して、原核生物から真核生物にいたる生物の系統関係を調べた。その結果、古細菌であるメタン細菌と真正細菌では、同じ原核生物の仲間でありながら、真核生物との差に匹敵するほど異なっていることに気がついた。そしてさらに多くの生物で詳しく調べ、ほとんどすべての生物は真正細菌,古細菌,真核生物という、大きくは三つの生物群に分類されることを明らかにした。真正細菌ドメインには一般的に知られている枯草菌,大腸菌や藍色細菌注3)が含まれ、古細菌ドメインには超好熱細菌,好塩細菌,メタン細菌などが含まれる。
黒岩常祥「細胞はどのように生まれたか」1999年
注1)16SリボソームRNA遺伝子のこと。
注2)18SリボソームRNA遺伝子のこと。
注3)ラン細菌,ラン藻類ともよぶ。
注:現在では、 イ 界には、単細胞生物以外にも比較的体制が単純な生物も分類されていますが、この問題では問題文に示された特徴をもつものとして答えてください。
問1 本文の ア ~ オ の空欄に適切な語句を記入せよ。
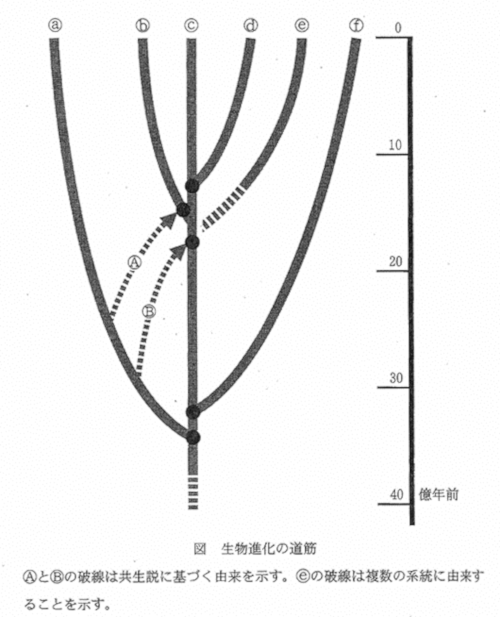
問2 図の系統樹に示したⓓは問1の エ 界、ⓔは イ 界に相当する。図中のⓐ~ⓒ,ⓕは五界のうちいずれに相当するか。適切な語句を記入せよ。
問3 図の系統樹に示したⓐ~ⓕは三ドメインのいずれに相当するか。適切な語句を記入せよ。
問4 図のⓑ,ⓒ,ⓓ,ⓔの各界の生物はⒶまたはⒷがそれぞれの時期に共生することにより進化してきたと考えられている。図の系統樹を参考に次の問に答えよ。
1)葉緑体とミトコンドリアの起源に相当するのはそれぞれ図中のⒶとⒷのいずれか。記号で答えよ。(半角アルファベットの大文字のみ入力すること)
2)Ⓑの方が古い時代に共生して新しい生物群が生じたと考えられ、図に示すような系統樹が描かれた。Ⓑの方が古い根拠について80字以内で記せ。
3)ⓑ,ⓒ,ⓓの各界の生物がもつ細胞小器官の有無について、それぞれ次の①~⑧に示す組み合わせの中からもっとも適切なものを一つ選び、記号で答えよ。①~⑧は、細胞核,ミトコンドリア,葉緑体の順に、それぞれの有無を表している。(半角数字のみ入力すること)
細胞核 |
ミトコンドリア |
葉緑体 |
|
① |
有 |
有 |
有 |
② |
有 |
有 |
無 |
③ |
有 |
無 |
有 |
④ |
有 |
無 |
無 |
⑤ |
無 |
有 |
有 |
⑥ |
無 |
有 |
無 |
⑦ |
無 |
無 |
有 |
⑧ |
無 |
無 |
無 |
重複受精と花粉管
※東京大学の入試問題を参考に作られています。
次の文を読み、各問に答えよ。
被子植物では、若いおしべの
柱頭で発芽した花粉からは花粉管が伸長し、助細胞から放出される花粉管誘引物質に導かれ、花粉管は珠孔へと到達する。その後、花粉管が胚のうへと進入する際には、1個の助細胞が崩壊し、2個の精細胞が胚のう内部に放出される。放出された2個の精細胞はそれぞれ、卵細胞,中央細胞と接合する。こうした受精様式を重複受精と呼ぶ。重複受精の結果、(イ)卵細胞は胚へ、中央細胞は胚乳へと発達し、正常な種子形成が行われることになる。
ある種子植物$C$種において、変異$m$のヘテロ接合体から得られる花粉では、50%の割合で花粉管内に2個の精細胞ではなく1個の精細胞に似た細胞がつくられる。こうした異常な細胞をもつ花粉管は、花粉管の内容物を放出するまでの過程に野生型との間で違いはみられないが、胚のう内に放出された精細胞に似た細胞は、卵細胞とも中央細胞とも接合することができず、正常な種子形成を開始することができない。$C$種の野生型株と変異$m$のヘテロ接合体を用いて、以下の実験を行った。
実験1 $C$種の野生型株の柱頭に変異$m$のヘテロ接合体から得た花粉を十分量受粉したところ、以下のような結果が得られた。
結果1 75%の胚のうで重複受精が成立し、正常な種子形成が観察された。
結果2 重複受精が成立した胚のうの67%では、進入した花粉管が1本であった。また、残りの胚のうでは2本の花粉管の進入が観察された。
結果3 重複受精が不成立の胚のうでは、すべて2本の花粉管の進入が観察された。
実験2 あらかじめ助細胞の1つを破壊した$C$種の野生型株の柱頭に、変異$m$のヘテロ接合体の花粉を十分量受粉したところ、以下のような結果が得られた。
結果1 50%の胚のうで重複受精が成立し、正常な種子形成が観察された。
結果2 すべての胚のうで、進入した花粉管は1本しか観察されなかった。
〔問〕
以下の小問に答えよ。
A 下線部(ア)について。(ア)の過程で卵細胞が作られるまでの、核あたりのDNA量の変化をグラフに示せ。なお、グラフの横軸には時間経過を、縦軸には核あたりのDNA量をとり、(ア)の過程が始まる前の時点における胚のう母細胞の核あたりのDNA量を2とすること。
B 下記の植物種の中から重複受精をする植物種をすべて選べ。(植物種は全角カタカナで入力し、間には全角の読点(、)を入力すること)
イチョウ,イネ,エンドウ,ゼニゴケ,ソテツ,ワラビ
C 下線部(イ)について。卵細胞,胚,胚乳それぞれの核相を記せ。(半角のみで入力すること)
D $C$種の野生型株では、受精した胚のうに進入している花粉管は1本しか観察されない。実験1,2の結果をもとに、$C$種の野生型株において花粉管が胚のうへ2本以上進入するのを防ぐ仕組みを考察した。以下の文章中の、空欄1~3に当てはまる適切な語を入れよ。
考察:$C$種の野生型株では、1本目の花粉管の胚のうへの進入により重複受精が成立する。この時 1 細胞からの 2 物質の放出が続くと、さらなる花粉管の胚のうへの進入が起きてしまう。これを防ぐために、重複受精が成立すると、 1 細胞の機能を 3 する仕組みが存在する。
E 実験1の結果1について。75%の割合で重複受精が成立する仕組みを3行程度で説明せよ。
(実際の解答用紙では、1行が縦0.6cm×横22.4cmとなっています)
ゲノムと遺伝子
※( )内の年度のセンター試験の問題を参考に作られています。(答えはすべて半角数字で入力すること)
問1 次の文章中の カ ・ キ に入る語として最も適当なものを、下の①~⑧のうちからそれぞれ一つずつ選べ。
(2017(平成29))
多細胞生物の各組織では、特定の遺伝子の カ の結果、組織ごとに異なるタンパク質がつくられている。例えば、ヒトのだ腺(だ液腺)の組織では
① 複製 ② 分配
③ 発現 ④ 合成
⑤ インスリン ⑥ ヘモグロビン
⑦ アミラーゼ ⑧ フィブリン
問2 ゲノムに関する記述として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。
(2015(平成27))
① ヒトのどの個々人の間でも、ゲノムの塩基配列は同一である。
② 受精卵と分化した細胞とでは、ゲノムの塩基配列が著しく異なる。
③ ゲノムの遺伝情報は、分裂期の前期に2倍になる。
④ ハエのだ腺染色体は、ゲノムの全遺伝子を活発に転写して膨らみ、パフを形成する。
⑤ 神経の細胞と肝臓の細胞とで、ゲノムから発現される遺伝子の種類は大きく異なる。
問3 次の文章中の チ ・ ツ に入る数値の組合せとして最も適当なものを、下の①~⑧のうちから一つ選べ。
(2015(平成27))
ヒトのゲノムは約30億塩基対からなっている。タンパク質のアミノ酸配列を指定する部分(以後、翻訳領域とよぶ)は、ゲノム全体のわずか1.5%程度と推定されているので、ヒトのゲノム中の個々の遺伝子の翻訳領域の長さは、平均して約 チ 塩基対だと考えられる。また、ゲノム中では平均して約 ツ 塩基対ごとに一つの遺伝子(翻訳領域)があることになり、ゲノム上では遺伝子としてはたらく部分はとびとびにしか存在していないことになる。
チ |
ツ |
|
| ① | 2千 |
15万 |
| ② | 2千 |
30万 |
| ③ | 4千 |
15万 |
| ④ | 4千 |
30万 |
| ⑤ | 2万 |
150万 |
| ⑥ | 2万 |
300万 |
| ⑦ | 4万 |
150万 |
| ⑧ | 4万 |
300万 |
細胞の観察と研究
※( )内の年度のセンター試験の問題を参考に作られています。(答えはすべて半角数字で入力すること)
問1 細胞の発見と細胞説の提唱に関する記述として最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。
(2012(平成24))
① レーウェンフックは、コルクがたくさんの小部屋からできていることを発見し、それらを細胞と名付けた。
② シュライデンは、自作の顕微鏡を用いて微生物を発見した。
③ フックは、「すべての細胞は細胞から生じる」という考えを提唱した。
④ シュワンは、動物の体が細胞からできていることを提唱した。
問2 光学顕微鏡を用いてオオカナダモの葉の細胞を観察した。次の文章中の ア ・ イ に入る数値として最も適当なものを、下の①~⑧のうちからそれぞれ一つずつ選べ。ただし、同じものを繰り返し選んでもよい。
(2018(平成30)・追試)
10倍の接眼レンズと10倍の対物レンズを使い、1目盛りが1mmの100分の1である対物ミクロメーターと、接眼ミクロメーターとを用いて、細胞の長さを測定した。その結果、細胞の長さは接眼ミクロメーターの6目盛りに相当した。このレンズの組合せのとき、接眼ミクロメーターの10目盛りは対物ミクロメーターの12目盛りに相当した。したがって、細胞の長さは ア μmである。また同じ10倍の接眼レンズと、40倍の対物レンズの組合せを用いると、同じ接眼ミクロメーターの1目盛りは、理論上、 イ μmに相当すると考えられる。
① 2 ② 3 ③ 6 ④ 36
⑤ 48 ⑥ 60 ⑦ 72 ⑧ 84
問3 単一の細胞として存在している真核生物として最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。
(2007(平成19))
① ゾウリムシ
② アオミドロ
③ ヒドラ
④ 大腸菌
光合成のしくみ
※( )内の年度のセンター試験の問題を参考に作られています。(答えはすべて半角数字で入力すること)
問1 光合成に関する次の文章中の エ ~ カ に入る物質名の組合せとして最も適当なものを、下の①~⑥のうちから一つ選べ。
(2015(平成27))
光のエネルギーを受けて光化学系Ⅱのクロロフィルから放出された電子は、光化学系Ⅰに受け渡され、 エ の合成に使われる。電子を放出した光化学系Ⅱのクロロフィルが還元される際には、チラコイド内の水分子は分解され、酸素と オ が生じる。また、光化学系Ⅱで生じた電子が光化学系Ⅰに伝達される過程で、ストロマ側の オ がチラコイドの内側に輸送される。チラコイド内に蓄積された オ が、ある酵素を通ってストロマ側に移動するときに カ が合成される。このようにして合成された エ や カ は、二酸化炭素を固定する反応で使われる。
エ |
オ |
カ |
エ |
オ |
カ |
|||
| ① | NADPH |
$\ce{H+}$ |
ATP |
② | NADPH |
ATP |
$\ce{H+}$ |
|
| ③ | NADP+ |
NADPH |
ATP |
④ | NADP+ |
ATP |
NADPH |
|
| ⑤ | ATP |
NADPH |
$\ce{H+}$ |
⑥ | ATP |
$\ce{H+}$ |
NADPH |
代謝に関する次の文章を読み、下の問い(問2~4)に答えよ。
(2005(平成17))
光合成により二酸化炭素から有機物が合成される経路は、放射性同位体$\ce{^{14}C}$を含む$\ce{^{14}CO2}$をクロレラ(緑藻)に与える実験により明らかにされた。クロレラの培養液に光を当てながら$\ce{^{14}CO2}$を与え、時間経過に従い、クロレラから光合成産物を抽出し、$\ce{^{14}C}$がどのような化合物に現れるかを調べた。図2はこの結果である。
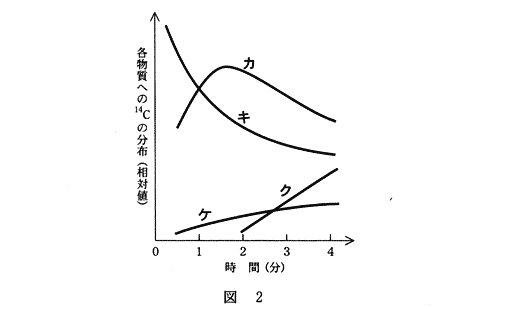
問2 図2の曲線カ~ケは、炭素を3個もつ$\ce{C3}$化合物,炭素を6個もつ$\ce{C6}$化合物,スクロース(ショ糖),アミノ酸への放射能の分布の時間経過に伴う変化を示している。このうち、ケはアミノ酸である。カ~クの組合せとして最も適当なものを、次の①~⑥のうちから一つ選べ。
カ |
キ |
ク |
|
| ① | $\ce{C3}$化合物 |
$\ce{C6}$化合物 |
スクロース |
| ② | $\ce{C6}$化合物 |
スクロース |
$\ce{C3}$化合物 |
| ③ | スクロース |
$\ce{C3}$化合物 |
$\ce{C6}$化合物 |
| ④ | $\ce{C3}$化合物 |
スクロース |
$\ce{C6}$化合物 |
| ⑤ | $\ce{C6}$化合物 |
$\ce{C3}$化合物 |
スクロース |
| ⑥ | スクロース |
$\ce{C6}$化合物 |
$\ce{C3}$化合物 |
問3 この実験で、$\ce{CO2}$の供給を止めると$\ce{C5}$化合物がたまり、光を消すと$\ce{C3}$化合物がたまった。この説明として適当なものを、次の①~⑥のうちから二つ選べ。ただし、解答の順序は問わない。
① $\ce{CO2}$と結合する化合物は、$\ce{C2}$化合物である。
② $\ce{CO2}$と結合する化合物は、$\ce{C3}$化合物である。
③ $\ce{CO2}$と結合する化合物は、$\ce{C5}$化合物である。
④ $\ce{CO2}$から$\ce{C3}$化合物ができる過程で光が必要である。
⑤ $\ce{C3}$化合物から$\ce{C5}$化合物ができる過程で光が必要である。
⑥ $\ce{C5}$化合物から$\ce{C3}$化合物ができる過程で光が必要である。
問4 この実験に関する記述として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。
① $\ce{^{14}C}$を含む化合物の分析には、電子顕微鏡が使われる。
② 炭酸同化経路にはATPや$\ce{〔H〕}$が必要な反応があり、光を消すとこれらの供給が抑えられるので反応は停止する。
③ 炭酸同化経路は暗反応であり、クロレラの培養液を暗所に長時間置いても進行する。
④ 炭酸同化経路は光化学反応であり、温度に依存しないが光の強さに影響される。
⑤ $\ce{^{14}CO2}$を長時間クロレラに与えると、最終的にはデンプンのみに放射能がみられる。
