この問題でおさえておきたいこと
チラコイド、ストロマそれぞれでどういう反応がされているかをおさえよう!
チラコイドでは3段階での反応、ストロマではカルビン・ベンソン回路内での生成物を重点的に確認しよう!
解答
問1 ① 問2 ⑤
問3 ③・⑤ 問4 ②
重要事項のまとめ
・光合成と葉緑体
光合成は葉緑体でおこなわれる。
葉緑体には、扁平な袋状構造のチラコイドと基質部分のストロマからなり、それぞれで、生成物をつくるなどの反応がある
・チラコイドでの反応
1.光化学系Ⅱ
光エネルギーにより、水が水素と酸素に分解し、電子$\ce{e-}$をうみだす
→酸素は外に放出
2.電子伝達系
電子が移動しているエネルギーを利用して、水素イオン($\ce{H+}$)はチラコイドの内側に運ばれ、チラコイド側とストロマ側で$\ce{H+}$の濃度勾配が生じる
→濃度勾配にしたがって$\ce{H+}$がATP合成酵素を通ってストロマ側へ移動するときにADPからATPが合成される(=光リン酸化反応)
3.光化学系Ⅰ
電子伝達系でストロマ側へ移動した水素イオンは、NADP+と結合し、NADPH+$\ce{H+}$となる。
・ストロマでの反応
カルビン・ベンソン回路とよばれる反応が起こっている
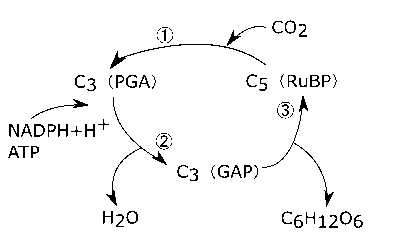
回路内での流れ
- ①での反応…
リブロースビスリン酸(RuBP)という名前の$\ce{C5}$(炭素が5個ある化合物)が二酸化炭素と反応してホスホグリセリン酸(PGA)という名前の$\ce{C3}$(炭素が3個ある化合物)に変化する
二酸化炭素をとりこむときに、リブロース二リン酸カルボキシラーゼ(RuBisCO)という酵素が必要
化学反応式:
$\small{\ce{6C5(RuBP) + 6CO2 -> 12C3(PGA)}}$ - ②での反応…
PGAが、光リン酸化でできたATPや光化学系でできたNADPH+$\ce{H+}$と反応してグリセルアルデヒドリン酸(GAP)という名前の$\ce{C3}$と水に変化する
化学反応式:
$\small{\ce{12C3(PGA) + 24H+ -> 6H2O + 12C3(GAP)}}$$\small{\ce{12C3(PGA) + 24H+ \\ -> 6H2O + 12C3(GAP)}}$ - ③での反応…
GAPが、いくらかのグルコース($\ce{C6H12O6}$)を生成しながらまたRuBPに戻る
化学反応式:
$\small{\ce{12C3(GAP) -> C6H12O6 + 6C5(RuBP)}}$
※チラコイドとストロマの各反応すべてを1つの化学反応式にまとめると、次のようになります。これが光合成全体をあらわす化学反応式です。
$\ce{12H2O + 6CO2 -> 6O2 + 6H2O + C6H12O6}$
解説
問1 「重要事項のまとめ」のとおり、光化学系ⅡではNADPH+$\ce{H+}$が合成されるので、 エ に入るのはNADPHで、光化学系Ⅰでは水が水素と酸素に分解されるので、 オ に入るのは$\ce{H+}$です。その$\ce{H+}$がストロマ側へ移動するときに光リン酸化反応が起こってATPが合成されますから、 カ にはATPが入ります。
問2 $\ce{C3}$とか$\ce{C6}$などが出ていますから、カルビン・ベンソン回路が関係していると考えることができますね。カルビン・ベンソン回路では$\ce{C6}$はつくられないと思われたかもしれませんが、グルコースには$\ce{C}$が6個ありますね?つまり、$\ce{C6}$とはグルコースのことと考えればOKです。
グラフを見ていると、まずキが多くなっていて、時間が経つにつれてキが減っていくと同時にカが増えていっています。そして、カが減っていくにつれて今度はケ、そしてクという順で増えていっていますね。ということは、これはキ→カ→クの順で物質がつくられていっているとわかるわけです。
この実験は$\ce{CO2}$が与えられるところから始まっているわけですから、カルビン・ベンソン回路で$\ce{CO2}$と反応することでつくられるホスホグリセリン酸(PGA)がまずつくられていくことになります。これは$\ce{C3}$でしたから、キは$\ce{C3}$化合物ということになります。
その後、グリセルアルデヒドリン酸(GAP)に変化したのちにグルコースができるわけですから、ここで$\ce{C6}$化合物ができるということになるので、カは$\ce{C6}$化合物といえます。これより、⑤が正解といえます。
ちなみに、スクロースは葉緑体内で合成されたグルコースなどの糖が細胞質基質に移動した後に合成されます。なので、一番最後に増えているクがスクロースといえるわけです。
問3 「$\ce{CO2}$の供給を止めると$\ce{C5}$化合物がたまる」ということは、$\ce{C5}$化合物が反応するには$\ce{CO2}$が必要ということです。つまり、$\ce{C5}$化合物は$\ce{CO2}$と結合して反応することになるので、③が正しいといえます(「重要事項のまとめ」でも、$\ce{CO2}$と結合しているのはリブロースビスリン酸(RuBP)という$\ce{C5}$化合物ですね)。
そして、「光を消すと$\ce{C3}$化合物がたまる」ということは、$\ce{C3}$化合物が反応するには光が必要ということですから、$\ce{C3}$化合物が何かに変わるには光がないとできないということになります。このことを最もよくあらわしているのは⑤です。
問4 ①:電子顕微鏡は細胞の形などを観察するときに用いるものであり、$\ce{^{14}C}$を含んでいるかどうかを判断するための放射能を測定するには適していません。
②:炭酸同化経路とは光合成のことです。光合成のカルビン・ベンソン回路ではATPや$\ce{〔H〕}$が必要ですし、チラコイドでの反応では光がないと反応が進まず、そうするとストロマ側でも反応は起きなくなります。よって、この文の内容は正しいです。
③:②の解説にもあるとおり、光合成は光がないと反応が進まないので、暗所に長時間置いたら反応は進みません。
④:たとえば、カルビン・ベンソン回路ではリブロース二リン酸カルボキシラーゼ(RuBisCO)という酵素が必要であり、酵素は温度の影響を受けます。よって、「温度に依存しない」とあるのは誤りです。
⑤:$\ce{^{14}C}$を与えると、反応にかかわるすべての物質に放射能がみられるようになるので、「デンプンのみ」にみられるというのは誤りです。