中学理科(生物・地学)の問題演習
令和7年5月1日
いろいろな花のつくり
※( )内の高校の入試問題を参考に作られています。(記号を答える問題は全角のカタカナのみを入力すること)
(1)アブラナの花を分解したところ、次の図のようになった。各問いに答えよ。
(島根県公立高校入試)
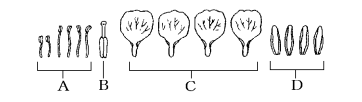
① 図のA~Dを何というか、それぞれ名称を答えよ。
② 図のA~Dを、花の中心から外側に向かって並べたとき、その順番を記号で答えよ。(半角アルファベットの大文字のみ入力すること)
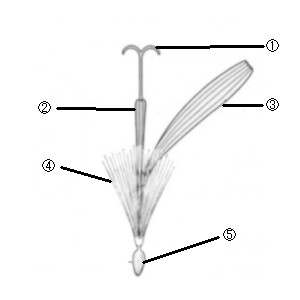
(2)キク科のタンポポは、被子植物の双子葉類である。タンポポは、図1の小さな花がたくさん集まり、1つの大きな花を形成する。次の問いに答えなさい。
(鹿児島・ラ・サール)
① 次のア~エは、図1の①~⑤のどの部分か。番号とその名称を答えよ。(番号については半角数字のみ入力すること)
ア 花粉ができる
イ 花粉が受粉する
ウ 種子ができる
エ 綿毛に変化する
② 次の文の(ア),(イ)に最も適する数値を答えよ。(半角数字のみ入力すること)
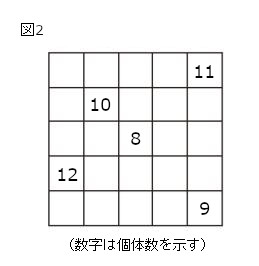
草原(200m2)に生えているタンポポの個体数を調べてみることにした。草原全体の個体数を実際に調べるのは大変なので、草原の一部(25m2)を25区画の正方形に区切り、このうち、ランダムに選んだ5区画について実際に個体数を調べた。1区画は、1m2にした。その結果を図2にまとめた。この結果から1区画あたりの平均個体数を求め、草原全体の個体数を推定することにした。1区画の面積は草原全体の面積の\( \displaystyle \frac{1}{\fbox{(ア)}} \)なので、草原全体の個体数は、1区画の平均個体数の\( \fbox{(ア)} \)倍となり、草原全体の個体数は、\( \fbox{(イ)} \)個体と推定される。
(3)植物に関する次の各問いに答えなさい。
(大阪・清風)
① エンドウと同じ「マメのなかま」の植物を、次のア~エから1つ選び、記号で答えよ。(全角のカタカナのみ入力すること)
ア ナズナ イ タンポポ
ウ シロツメクサ エ アサガオ
② 主根の有無・花びらのようす・子房の有無について、それぞれエンドウと同じものが記されている欄を、表1のア~オから1つ選び、記号で答えよ。(全角のカタカナのみ入力すること)
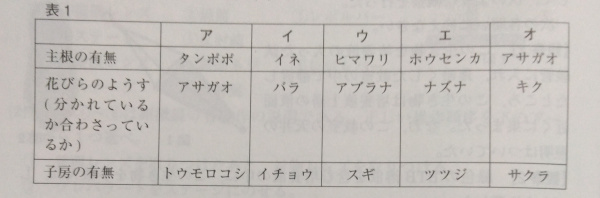
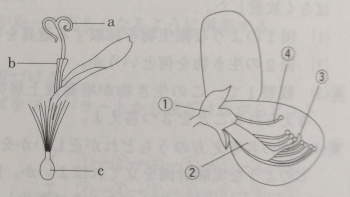
③ 右図は、タンポポとエンドウの花を模式的に示したものである。タンポポのa・b・cの各部分をエンドウの①~④の部分に正しく対応させたものを、表2のア~クから1つ選び、記号で答えよ。(全角のカタカナのみ入力すること)
ただし、エンドウの模式図は花びらの一部を取り除いてある。
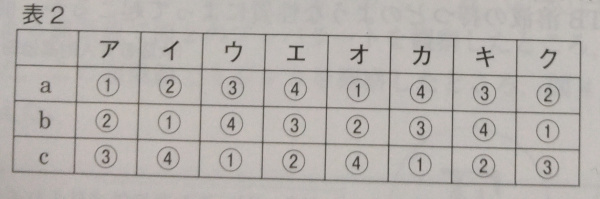
(4)多くの花において、花弁は色あざやかで目立ちやすい。その理由について、植物が受粉するしくみを考えて説明せよ。
(島根県公立高校入試)
令和6年11月3日
太陽系の惑星
※福岡県の西南学院高校の入試問題を参考に作られています。(記号を答える問題は全角のカタカナのみを入力すること)
下の表は、現在知られている太陽系の惑星を小さい順に並べ、いろいろな特徴を示したものである。これらについて以下の問いに答えなさい。
惑星名 |
惑星の半径 |
密度 |
公転周期 |
Xの数 |
a |
0.38 |
5.4 |
0.24 |
0 |
b |
0.53 |
3.9 |
1.88 |
2 |
c |
0.95 |
5.2 |
0.62 |
0 |
地球 |
1.00 |
5.5 |
1.00 |
1 |
d |
3.9 |
1.6 |
164 |
8 |
e |
4.0 |
1.3 |
84.0 |
20以上 |
f |
9.4 |
0.7 |
29.5 |
30以上 |
g |
11.2 |
1.3 |
11.9 |
39以上 |
(1)上の表の惑星は、いずれも輝いて見える。この理由として、最も適当なものを次の中から1つ選び、記号で記せ。
ア みずから光を出しているから。
イ 太陽の光を反射しているから。
ウ 月の光を反射しているから。
エ 1つの惑星が出す光を反射しあっているから。
オ いくつかの惑星が出す光を反射しあっているから。
(2)表のXにはどのような語句があてはまるか。適語を記せ。
(3)太陽系で最も大きい惑星(表のg)は何か。名称を漢字で記せ。
(4)地球の約9倍の直径をもつにもかかわらず、密度が水よりも小さい惑星(表のf)は何か。名称を漢字で記せ。
(5)表からわかることとして正しいものを次の中から1つ選び、記号で記せ。
ア 地球より外側を公転する惑星の半径は、地球の直径より大きい。
イ 地球より半径が小さい惑星は、公転周期が地球より短い。
ウ 公転周期が長い惑星ほど、半径が大きい。
エ 公転周期が2年以内の惑星は、密度が3g/cm3より大きい。
